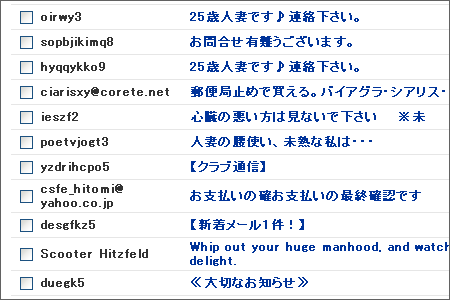ラベンダーの入浴剤を湯船にダポン、と落とす。細かな泡が、ふくらはぎをくすぐるように撫で上げる。はああ。大きなため息が出た。ここ数日、ずっしりとした疲労が体内に横たわっていて動こうとしないのだ。はああ。今度は湯船へ顔を浸しながら、ため息をついてみる。ボコンボコンと大きな気泡が2つ、水面に弾けた。
誰もが美津子の美貌を褒め称えた。黒木瞳に似ているともっぱらの評判だった。悪い気はしなかったが、目立つのは嫌いだった。この年になってもナンパは日常茶飯事だし、魚屋の主人は決まって貝類をおまけで握らせてくるし、果物屋の主人はむいたバナナを「美容にいいから」とその場で食べさせようとするし、犬の散歩をしていると白くて気味の悪い警官が遠くからじっとこちらを見ていたりする。こないだなんかは「おキレイな方のほうが、なにかと、ねえ?」よくわからない理由でPTA会長を押しつけられてしまった。それでも、マコトのため、愛する息子のためなのだと自分に言い聞かせ、引き受けることにした。
入浴剤はコトコト音を立てながら膝の裏を撫で、脇の下を撫で、いつの間にか美津子の背後へと移動し、しばらくのあいだ背中を撫で続けた。しゃわわー。痩せ細った入浴剤が赤と青とに色素を分離させながら水面に浮上する。美津子はその毒々しい色彩を観察するために顔を近づけると、微細な泡沫に形を変えた香料が、鼻腔を強烈に刺激した。痛い。美津子は、ものすごく体に悪いものを吸い込んでしまった気がして、犬のように何度も鼻をフンッとやった。
しゃわしゃわと最後の力を振り絞る入浴剤。自らの存在を消滅させるべく躍起になっているその姿は健気であり、いじらしくもあり、そして腹立たしくもあった。「しゃわしゃわしないで!」美津子は入浴剤をバシャンと水中へ押し込めた。
静寂を取り戻した水面を眺めながら、はああ。3度目のため息をつく。そして、水面から顔を覗かせた膝頭を何気なく見つめていると、美津子は気づいてしまった。皮膚が、まったくと言っていいほど水を弾いていないことに。だらしなくへばりついたままの湯水。なによこれ。顔を背けるつもりで胸元に目を移したが、そこには、より面積の大きい不安材料が広がっているだけだった。
「オユハリヲ、カイシシマス」美津子は瞬時に操作パネルへと手を伸ばし、首から下が隠れるまで、いや、湯船から溢れ出してしまうまで、お湯を張り続けた。美津子は、ゆっくりと失われてゆくラベンダーのうす紫に気づくこともなく、上昇してゆく水位を、ただただ眺め続けていた。